ヒラタクワガタ
Dorcus titanus pilifer
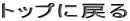
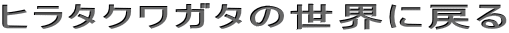

国内では東北南部以西に広く分布する。成虫は湿度が良く保たれた環境を好む。夏季に樹液に見られるが、日中は樹皮の隙間などに隠れている。人の気配にはやや敏感で、すぐに隠れてしまう個体も多い。
九州北部から山口県にかけて分布する個体は、本州中部などに分布する個体と比較すると、大顎が長い個体が多い。最近のDNAによる分類でも、九州北部から山口県にかけての個体群は、その他の地域の個体群とやや離れた位置にいるようだ。
大型の個体では70mmを超えることがあるが、野外で見られる個体は60mm以下の個体がほとんどになる。東京都内のような都市部でも昔から生息していて、現在でも見られる地域がある。
飼育は簡単な種類になるが、♂は交尾をいやがる♀を攻撃することがあるため注意が必要だ。飼育方法はこちら(飼育方法
ヒラタクワガタ)を参考にしてください。
本州の中部以西で普通に見られるようになるが、関東地方から東北地方南部では分布も局地的で個体数も少なくなる。南方系のクワガタで西日本産の個体の方が大きくなるし、暖かい方がこの種にはあっているようだ。ノコギリクワガタと共に特化しやすいようで、離島に分布しているヒラタクワガタは亜種になっている個体群が多い。
中部以西では夏季樹液で普通に見られ、幼虫は湿度が高い地表部の朽ち木や埋設木で見られる。関東では局地的になるが、ポイントを掴めば採集できる場所は多い。関東地方の平野部は気候区分帯に分ければ暖帯で、極相林になるとシラカシの純林になる。現在関東地方に残っている林はほぼ全て二次林で、人間が生活と共に手を加えてきた林だ。残念ながら現在ではほとんど使われなくなってしまったが、落ち葉は腐葉土として畑にまく肥料に、クヌギやコナラの幹や枝は炭焼きの原料にしたり、クヌギの枝葉は刈り敷きの肥料として用いられてきた。ヒラタクワガタに限らずほとんどのクワガタは原生林より人手が多少入った林を好むが、関東地方では畑や水田の周りに残された林で枯れてしまった木の地中部に幼虫が、成虫はクヌギやコナラの樹液を吸いながら世代を重ねて来たはずだ。関東地方でヒラタクワガタが見られる地域は昔からの林が残されている場所や、河川敷などの昔からの環境があまり変わっていない場所で見ることが出来る。カシの大木やクヌギ、コナラの大木が残されていて、湿度が良く保たれたある程度の広がりを持つ林を捜してみると以外に見られる場所が多い。
ヒラタクワガタは暖帯から熱帯にかけて分布しているクワガタで、関東地方から東北地方南部は分布の北限に当たる。カシの木の分布とよく似た分布をしているが、ヒラタクワガタは冬の間の最低気温で越冬できるか出来ないかで分布が決まっているようだ。成虫、幼虫共に完全な越冬態にはなれないようで、氷点下になると体の組織が凍ってしまい死亡してしまう。高山帯のクワガタなどは冬になると半透明になってじっとしているが、濃いめの糖分かグリセリンで体を満たし、組織が凍結しないように工夫して越冬している。ヒラタクワガタは熱帯生まれのクワガタのせいか、このような状態になることが出来ず、死亡してしまうためだ。競合種のノコギリクワガタが減ったためとも言われているが、最近では温暖化のせいもあってか、関東地方でもヒラタクワガタが増えてきている。以前は見られる個体は大きくても40mm程度の個体だったが、最近は60mm程度の個体も見られるようになった。大型の幼虫の方が低温には弱いため、最近の温暖化の影響で大型になっても越冬することが出来るようになったためだろうか。








→次のページは拡大写真
当サイトの画像、文章を無断使用、転載することを、堅くお断り致します
Copyright(c)
2004 [AtoZ] All Rights Reserved.
Since 2002 Jun.
|











